-
お知らせ
- 休診のお知らせ
※終日休診: 令和8年2月9日(月)、2月10日(火)、2月14日(土)
※午後のみ休診 : 2月13日(金)
※令和8年3月4日(水)院長出張のため休診となります。
- 土曜日はアレルギー外来のみの診療となります。発熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢などの感染症の診療は行っておりません。
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
- ブログを更新しました!
last update 2026/01/06
18回目
-
アレルギーに関する心配事、講演依頼など、お気軽にお問合せください。
>>こちらから
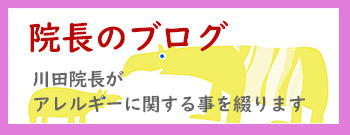
-
食物アレルギー

- 血液検査やプリックテスト(皮膚アレルギー検査)を行うことができます。
- 食物アレルギーの発症予防に力を入れています(乳児アトピー性皮膚炎の治療等)。
- 食物経口負荷試験(OFC; Oral Food Challenges)について
(1)年間実績3000件以上
(2)すべて単回摂取となっています
(3)症状誘発率
;2%以下(アナフィラキシーは年に1-2件程度です)
(4)閾値(いきち)が低い症例、アナフィラキシー歴がある症例、完全除去症例、ナッツ類等の負荷、これらの症例に対しても、安全に症状を出すことなくOFCを実施することが可能です。
(5)(コロナ前には、)遠方(静岡県浜松市外、愛知県、岐阜県、滋賀県、東京都、神奈川県等)からの患者さんが多数当院のOFCを経験されています。
- エピペンが必要と判断された患者さんには個別に丁寧な指導を行います。
- アナフィラキシーショック時の症状や対応について丁寧に説明いたします。
- 院長、スタッフは、市内の保育所や小中学校の先生方への食物アレルギーの講習を行っております。
- 成人食物アレルギー患者さんも診療可能です。
